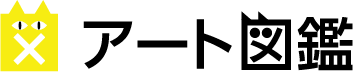ハイソのためのアート“だけ”じゃなく、自分のためのアートも
アートはステータス「ではない」と言い切るより、こう言ったほうが正直かもしれない。
アートはステータスとして見られることもあるし、同時に、自分と向き合うきっかけにもなる。
アートが好きです」と口にすると、どこかで「ハイソっぽい」「教養がありそう」と受け取られることがある。そういう空気があるのは、たぶん事実だと思う。だからこそ、アートを楽しむ気持ちの中に、ほんの少し「よく見られたい」が混ざってしまうのも、そこまで不思議なことではない。
*「ハイソ」とは、もともと “ハイ・ソサエティ(high society)”=上流社会 の略。上品ぶっている/お金持ちっぽい/おしゃれで教養ある感じなど、ちょっと「庶民とは違う世界」の雰囲気を表した俗語的な言い方
美術館に通っている。
有名な展覧会はだいたいチェックしている。
アートの本を読み、SNSで感想を発信している。
こういう営みは、どれも素敵だと思う。誰かに見せるためじゃなく、ただ好きでやっている人もたくさんいる。ただ同時に、「アートを知っている自分」「語れる自分」を通して、少し安心したくなる瞬間がある人もいるかもしれない。
それは“間違い”というより、自然な心の動きに近い。
人は誰だって、どこかで「私はこれでいい」と思える拠り所が欲しいからだ。
ただ、もしその安心が大きくなりすぎると、作品そのものがくれる揺れや発見よりも、「どう見えるか」「どう評価されるか」が前に出てきてしまうことがある。
この文章は、そこを責めたいのではなく、そっと立ち止まって見直すためのものだ。
では、なぜそうなりやすいのか。
そこには個人の性格というより、アートが置かれてきた歴史や、社会の空気が関係している部分がある。
アートが「ハイソ」に見えやすい、歴史の名残
アートは長い間、王や貴族、教会、資本家といった「力のある側」と一緒に語られてきた。宮殿の天井画も、豪邸にかけられた油絵も、その背景には権力や富があった。
その記憶が文化として残っている以上、「アート=上品/お金持ちの世界」という連想が起きやすいのは、ある意味当然でもある。
高額での売買が大きなインパクト
ニュースで話題になるのは、作品の中身というより「いくらで落札されたか」という金額のほうだったりする。
高級ホテルや百貨店など、特別な場所でアートに出会うことも多い。そう考えると、日常で触れる“アートの断片”が「高価」「希少」と結びつきやすいのも無理はない。
かくいう筆者も幼少の頃は絵が得意でよく賞をもらっていたのだが、周りの友人や大人から、「ゆくゆくは有名になり高く売れるようになるかもだから1枚もらっておきたい」などの言葉をかけられたことは1度や2度ではない。言った側に悪気がなくても、そうした言葉が「価値=値段」という見え方を強めてしまうことはある。そして自分自身も、褒められることが嬉しくて、どこか「評価されるため」に描いていた部分があった気がする。
つまり、「アート=ハイソ」という連想は、誰かの性格の問題というより、長い時間をかけて育ってきた「見方のクセ」でもある。
「教養の証明」としてのアート
日本の教育では、美術を「感じる」より先に「知る」ものとして学ぶ場面が多い。
この絵を描いた画家は誰か。どの時代か。どの流派か。どこに所蔵されているか。
テスト(競争)を長年続けてきた結果
テストで問われるのは、作品が自分に何を感じさせるかではなく、「覚えているか」だ。こうして「アート=覚える対象」というイメージが形成される。有名な作品を知らない場合は「そんなことも知らないのか?」と冷ややかな目を向けられることもある。「知っていることは紳士淑女の教養なのだよ。」と。
作品を覚えられるなら、周りと差がつけられる。差がつくなら、優劣が生まれる。やがて、「アートを知っている=教養がある」が成り立ってしまう。これは当然、日本の義務教育のあり方に課題は及ぶだろう。
日本の義務教育のあり方
大人になってからも、その延長線上で世界を見がちだ。
「この画家は○○派でね」と語れる自分。
「この美術館の企画はいつもレベルが高い」と言える自分。
そういう“わかっている風の自分”を演じられるようになると、ちょっとだけ安心する。自分には教養がある、自分はこの話題で評価されている、と確認したくなる。日本の義務教育が育んだのは「こうあるべき」という虚像と「他人の評価軸」というものさしだ。
その「他人のものさし」で評価される安心感自体を、いきなり否定することはできない。人は、自分の価値を確認できる場所をどこかに持っていないと、簡単に不安に飲み込まれてしまうからだ。ただ問題は、その確認作業が繰り返されるうちに、アートが“自分を守るツール”に変わってしまい、本当の効果というか、価値が見えなくなってしまううことだ。
「センスの証明」が欲しくなる空気
もう一つ、見逃せないのが、人間社会が「ラベル・記号」で人を測りたがる世界だということだ。「タグ」と言ってもいい。
学歴、肩書き、年収、住んでいるエリア、持ち物、行きつけの店。そういったものは、他人を瞬時に分類するための記号として消費される。大昔は身分や家系、地域、差別といったものも大変強かった。
この社会の中で、「アートに詳しい」「美術館によく行く」というのは、かなり魅力的なラベルの方ではないか。文化的で、感性が豊かで、どこか品があるように見える。いわば、「センスの証明」のような役割なのかもしれない。
日々の仕事に追われながら、「自分は何者なのか」「このまま年を重ねた先に何が残るのか」とどこかで不安を抱えている人ほど、その証明が欲しくなる。
仕事もそこそこ頑張っている。でも、それだけではどこか味気ない。もう少し“物語のある自分”でいたい。そのときに、「休日は美術館へ」「話の端々に画家の名前が出てくる自分」は、とても都合のいい安心材料になる。
「アートが好きな自分」は、その人の本音かもしれないし、同時に「そうでありたい自分」の演出でもあり得る。それ自体は否定しないし、むしろ、もっと「アート好き」が増えて欲しいので良いとも思う。
問題は、その境界が自分でもわからなくなっていくことだ。いつの間にか、「アートと向き合っている自分」よりも、「アートを知っている自分」の方を大事にしてしまう。
「正解のある世界」に慣れすぎた私たち
さらに根っこまで降りていくと、「正解のある世界に慣れすぎている」という問題にぶつかる。
学校ではテストに正解があり、仕事ではKPIや評価基準がある。努力すればある程度、結果が数字で返ってくる世界。
そこに長く浸っていると、「自分の感覚で決めていい」あいまいな領域に出るのが途端に怖くなる。そして、評価もできなくなる。定量的に〜、数字に対してのコミットメント〜などお決まりのフレーズが並ぶ。
「正解らしきもの」を探し始める
誰も正解がわからない。その不安から逃げるために、人は「正解らしきもの」を探し始める。
学芸員の解説、批評家の言葉、パンフレットの文章、SNSでバズっている感想。そこに寄りかかっていれば、とりあえず外さない。少なくとも、「わからない」と正直に言って馬鹿にされるリスクからは逃れられる。
こうして、「作品を見る」という行為は、いつの間にか「正しそうな感想を探してなぞる」行為にすり替わっていく。目は絵を見ているようでいて、実はずっと他人の視線と評価を見ている。
「自分の感覚で決めていい」あいまいな世界
アートは、その「自分の感覚で決めていい」あいまいな世界の代表だ。根拠やエビデンス、理由は必ずしも必要ではない。
また、何を好きになるかも、何に違和感を覚えるかも、誰も教えてくれないし、誰も点数をつけてくれない。それは自由であると同時に、ひどく不安定だ。
ステータス鑑賞の内側で起きていること
「ハイソな趣味」「教養の証明」「センスの免許証」としてアートを扱う人を、ここで裁いたところで何も前には進まない。むしろ大事なのは、その人たち(そして時に自分自身)が、どんな恐れや不安を抱えているのかを見つめ直すことだ。
「バカにされたくない」という恐れ
そこには「バカにされたくない」という恐れ、「自分の価値をどこかにくくりつけておきたい」という願望、「正解のない世界で迷子になりたくない」という防衛本能がある。言い換えれば、アートをステータスにしてしまう人は、アートが本来向けてくる“よくわからない揺さぶり”に、まだ耐えられないだけなのかもしれない。
本物の揺さぶりは、「正しいかどうか」「褒められるかどうか」とは別のところで起きる。
なぜか目が離せない。
理由もなくイライラする。
見ていると苦しくなる。
時間を忘れて眺めてしまう。
そういう、説明のつかない反応は、「この作品の価値は〜」とウンチクを語るときには邪魔者だ。うまく整理できないからだ。でも、その邪魔者こそが、アートの本体に一番近い。そこには、評価も点数もない。ただただ、自分自身の感情と記憶と価値観がむき出しになるだけだ。
ステータス鑑賞は、そのむき出しになる瞬間から目をそらすための、ある意味とても器用な防衛装置だ。だからこそ、それを全否定するのではなく、「いま自分は防衛装置をフル稼働させているな」と気づけるかどうかが分かれ目になる。
「よくわからない」を許容しましょう
では、ステータス鑑賞から一歩離れて、アートを「自分と向き合う装置」として使うにはどうしたらいいのか。特別な修行が必要なわけではない。ただ、いくつか「やめること」がある。
ひとつは、「すぐに意味を求めること」をやめることだ。
・この絵は何を象徴しているのか。
・このモチーフの裏にはどんな社会批判があるのか。
そういう問いは、興味が湧いてきたら後からいくらでも掘ればいい。けれど最初の一歩としては、「意味を理解する前に、自分に何が起きているか」を眺める方がずっと大事だ、と思う。自然の風景を鑑賞する時と似ている。
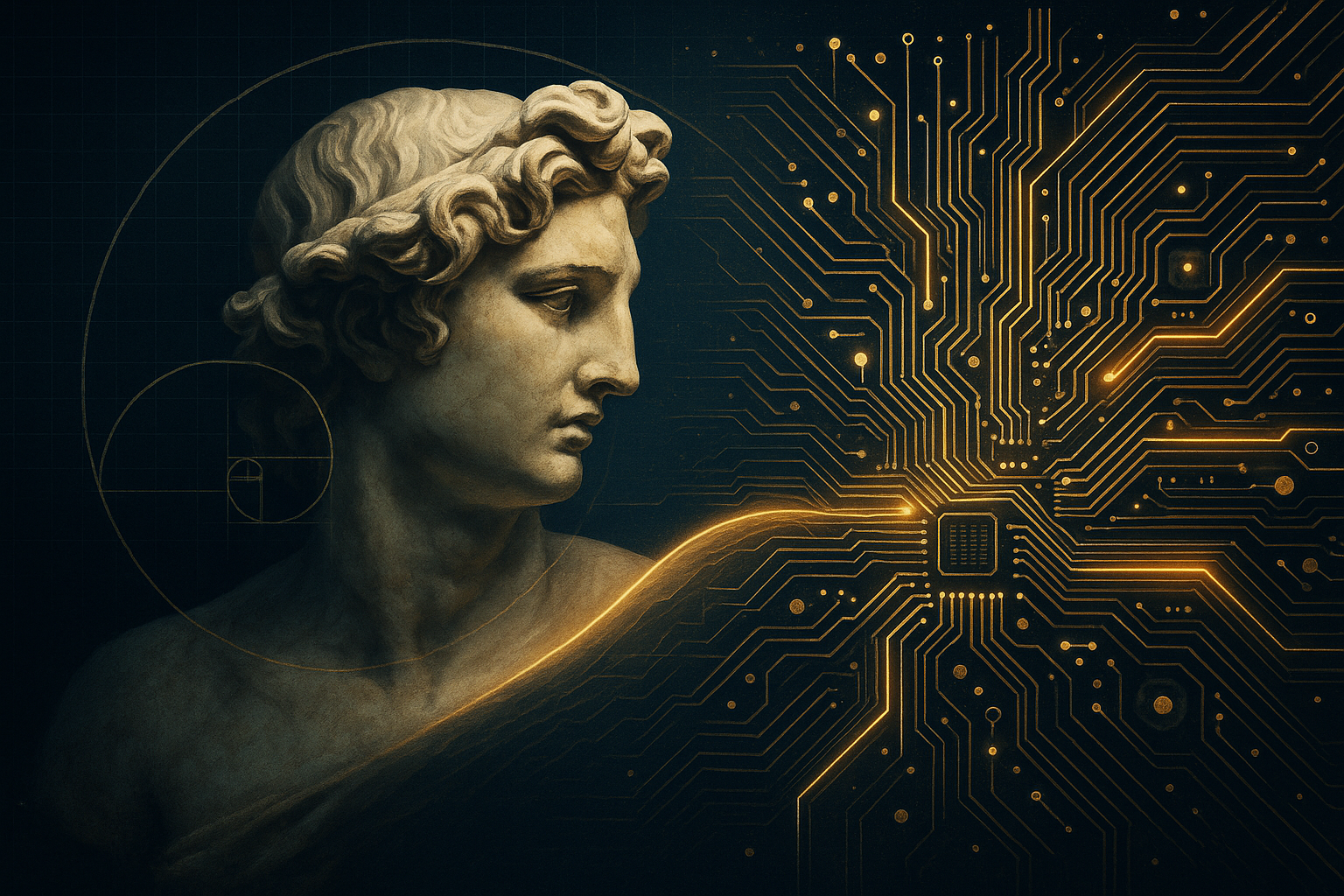
作品の前に立ったとき、自分の視線がどこに吸い寄せられたのか。身体が前に出たのか、むしろ引いたのか。心のどこかが、ざわついたのか、静まったのか。言葉にならないその変化を、ただ「ある」と認めることから始める。
もうひとつは、「正しい感想を言おうとすること」をやめることだ。
「すごくよかった」と言うべきだろうか。
「色彩が素晴らしい」と言っておけば無難だろうか。
そんな計算をいったん横に置いて、「よくわからない」「ちょっと苦手」「見ていたら泣きそうになった」といった生の感想を自分の中だけでも許す。誰かに共有する必要はない。自分だけのメモでいい。
そのとき、「好き/嫌い/どちらでもない」という、乱暴なほど大雑把なラベルを自分のためだけに貼ってみるのもいい。理由は言葉にならなくてもかまわない。言葉にならないまま残る感覚は、じわじわ時間をかけて、自分の中の何かと結びついていく。
そうして後から、「なぜあの絵はあんなに気になったんだろう」と振り返るとき、初めて知識や解説が役に立つ。画家の生涯や時代背景、技法の特徴を知って、「だからか」と腑に落ちることもあるし、「それでも自分はこう感じる」と、他人の説明と自分の感覚を並べて眺めることもできる。
大事なのは、知識が自分の反応を補強するためにあることであって、正解を先に与えてしまうためにあるのではない、ということだ。
アートは「自分の輪郭」を少しだけはっきりさせる
歳を重ねるほど、自分が何に癒やされ、何に傷つき、何に怒り、何に救われるかは変わっていく。若いころにはまったく響かなかった作品が、ある日突然胸に刺さることもあるし、かつて大好きだった絵が、今見ると不思議なくらい何も感じさせなくなることもある。
その変化は、言葉にすると「好みが変わった」で片づけられてしまう。でも、もう少し丁寧に見てみると、それは人生の輪郭が少しずつ描き変わっていくプロセスでもある。
失恋を経験したあとに見る肖像画。
子どもが生まれたあとに見る家族の絵。
親を亡くしたあとに見る風景画。
同じ作品でも、自分の状態によって全く違う顔を見せてくる。そのとき、アートは教養の飾りではなく、自分の現在地を測る装置として働いている。
だからこそ、「アートを知っている自分」や「アートに詳しい自分」を守るために、作品との間に壁を作ってしまうのは、あまりにももったいない。壁を作っている限り、作品は本気で向き合ってくれない。痛くも痒くもない。その代わり、自分の感情も深くは動かない。
ほんの少しだけ心の隙間を開ける。
「わからない」と感じる自分を許す。
「これは嫌いだ」と思ってしまう自分を否定しない。
「うまく説明できないけど、ずっと気になる」を大事にする。
その小さな許しを積み重ねることで、アートはゆっくりとステータスから解放され、静かな装置として機能し始める。作品はもはや、「ハイソな趣味」の証明でも、「教養のテスト」でもない。ただ、あなたの輪郭を少しずつ浮かび上がらせるための鏡になる。
アートは自由だ
アートをどう使うかは、本来ひとりひとりの自由だ。ハイソぶるために使うのも、誰かに見せるために使うのも、やろうと思えばいくらでもできる。でも、もしどこかで物足りなさを感じているなら、そろそろそ「そう考える自分」と正面から向き合ってもいいのかもしれない。